『なぜ人と組織は変われないのか―ハーバード流 自己変革の理論と実践』を読んでみたよ
今回読んだのは『なぜ人と組織は変われないのか―ハーバード流 自己変革の理論と実践』なんだ。以前紹介した『なぜ部下とうまくいかないのか』の著者の「加藤洋平」さんが、大学で発達理論を教わった先生のロバート・キーガンさんの本になるんだよ。
まずは目次だよ
目次はこんな感じになっているんだ。
序章 個人や組織は本当に変われるのか?
第1部 “変われない” 本当の理由
第1章 人の知性に関する新事実
第2章問題をあぶり出す免疫マップ
第3章 組織の「不安」に向き合う
第2部 変革に成功した人たち
第4章 さまざまな組織が抱える悩みI集団レベルの変革物語
第5章 なぜ部下に任せられないのか?─個人レベルの変革物語①
第6章 自分をおさえることができるか?─個人レベルの変革物語②
第7章 うまくコミュニケーションが取れないチーム─集団を変革するために、個人レベルで自己変革に取り組む物語
第3部 変革を実践するプロセス
第8章 変わるために必要な3つの要素
第9章 診断─「変われない原因」を突き止める
第10章 克服─新しい知性を手に入れる
第11章 組織を変える
終章 成長を促すリーダーシップ
第一部で理論を説明して、第二部で事例をもとに詳細を説明して、第三部で具体的な手順を説明していいるんだ。事例を読むのが苦手な人は大変かもしれないけど、事例の中に説明が入っているので飛ばさずに読んでほしい感じなんだ。
アドラー心理学との共通点を感じたんだ
まずこの本を読んで一番最初に感じたのは、アドラー心理学との共通点だったんだ。
本書で繰り返し“変革をはばむ免疫機能”ってキーワードが出てくるんだ。簡単に説明すると、「人や組織が変革できないとき、そこには裏の目標や固定観念がある」って事なんだけど…。これって、アドラー心理学の目的論とベーシック・ミステイクスと基本的に同じだって感じたんた。
アドラー心理学流に言うと…「『人や組織が変革できない』とき、現状を維持するだけの目的がある」って感じかな。その目的は、人や組織それぞれだけど…現状を維持することで、自覚できていないけど何かしらの恩恵を受けているんだよね。
ロバート・キーガンさんはこれを「守る(つまり免疫)」って表現しているんだ。今まで色々な人にアドラー心理学の目的論を説明してきたけど…「守る」って表現はしてこなかったんだ…今度からこれ使おう…(笑)
そして、その目的の根源には、強い固定観念があるって。アドラー心理学の言うところのベーシック・ミステイクスだよね。今の言葉で言うと、認知バイアスとかかな。でも、アドラー心理学とは大きく違うところがあるんだ。
ベーシック・ミステイクスだと、誤った固定観念って言っているから、はなから「間違っています」って言っちゃってるんだよね。でも、ロバート・キーガンさんは、この強い固定観念を頭ごなしに否定したりしてないんだ。
どう言うことかというと、ロバート・キーガンさんは、その強い固定観念を検証しなさいって言ってるんだ。「間違っている/合っている」って事じゃなく…もしかしたら解釈が変わるかもしれない…って。間違ってたら正せば良いし、解釈変わったならそのままでも良いって。この辺、人間味が有って、好感持っちゃうな(笑)
変革するための手法
この本には“変革をはばむ免疫機能”を「変革するための手法」も紹介されているんだ。
以前紹介した「なぜ部下とうまくいかないのか」では、「人の発達段階ごとに日常で使える手法」が紹介されていたんだ。でも、本書は「すべての発達段階で使用できるワークショップ」が紹介されているんだ。しかも、個人にもチームにも適用できるワークショップなんだよ。
ただ…本気で自分の心を観察・表現しないとならないので、他者に合わせることを美徳とする(自分の想いを見なかったことにする)多くの日本人にはちょっとハードルが高いかも…(^_^;) そういう意味では、自分の想いを言語化するトレーニングが先かもしれないね。
自分の想いを言語化するトレーニングというと内省(リフレクション)ってなるんだけど…。これもなかなか難しくって、「ありたいと願う自分の想い」と「本当の自分の想い」がごちゃまぜになりやすいんだよね。「気づけなかった」のか「無視した」のか…「言ってしまった」のか「言いたかった」のか…「やってしまった」のか「やりたかった」のか…本当の自分を見つめないと分からないよね…。
1つだけ引用したいんだ
最後に勇気がもらえる言葉が載っていたので紹介するんだ。と言っても、ロバート・キーガンさんが引用している言葉なんだけど…
ハイフェッツに言わせれば、リーダーが犯す最も大きな過ちは、適応を要する課題を解決したいときに技術的手段を用いてしまうことだ。適応を要する課題に立ち向かっているのに、その課題が技術的な課題だと「誤診」し、目指している変化を起こせないケースがしばしばある。適応を要する課題を解決したければ、適応型の(つまり技術的でない)方法を見いださなくてはならない。
ここで言う「課題」は、今発生した課題だけでなく、改善できない継続的な課題や諦めて課題と認知できなくなった課題のことを言っているんだ。
「技術的手段」は、課題を直接的に解決しようとする手法…例えばルールや規則・便利なツールのことを言ってるんだ。人為的バグが出たときの、チェックリスト作成なんかはこれに当たるね。
「適応」は、「適応障害」の適応と同じ意味なんだ。順応とだいたい同じ意味だよ。「適応障害」を調べて、今気がついたんだけど…「適応を要する課題」を「技術的手段」で解決しようとすると、「適応障害」が起こる可能性が高くなるんじゃないかな…無理やり「技術的手段」をやらせると、病人製造機になりかねないってことか…。
変革に関わっている人は読んでおくべき!
『なぜ部下とうまくいかないのか』と同様に、この本も従業員満足度向上に関わっている人に是非読んでいただきたいと思ったんだ。従業員満足度向上に関わっている人に限らず、「自分を変えたい」「組織を変えたい」「会社を変えたい」などなど、“変革”に関わっている人は是非一読してみてほしいんだ。

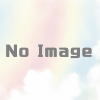


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません